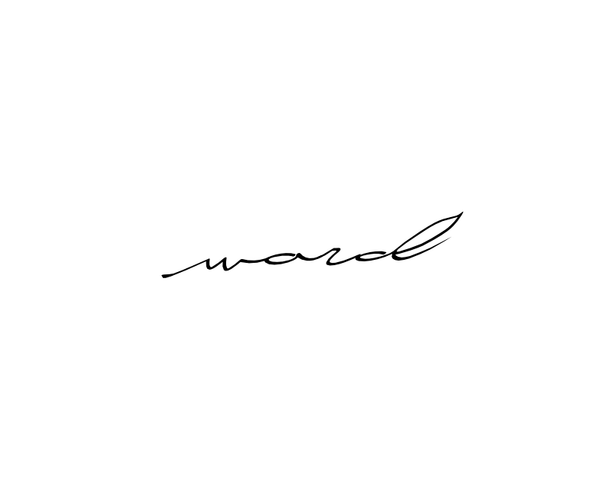The Landscape of Taste:味覚と、景色と。
The Landscape of Taste:味覚と、景色。
"最も美味しいと思えるCoffeeは、人それぞれ"
今回は味覚の違いとは何か、それが個人の嗜好性、Coffeeの好みにどの程度影響するのか、そしてそこから見えてくる景色について、詳しく考えていきます。
誰もが経験している「味覚の違い」
例えば友人と同じ料理を食べているとき、ひとりは「美味しい」と言い、もうひとりは「ちょっと苦手かも」と言う。そんな経験は誰にでもあるはずです。
典型的な例がパクチー。ある人には爽やかな香り、ある人には「石けんの味」。
これは、嗅覚受容体遺伝子(OR6A2)の違いが原因で、香り成分(アルデヒド類)の感じ方に差が出ると説明されています。
また、ゴーヤの苦味やビールのホップ感も人によって全く印象が違います。科学的には「PROPテスト」という実験で苦味の感じ方を測定でき、以下のように分かれることが知られています。
• スーパーテイスター(約25%):強烈な苦味を感じる
• ミディアムテイスター(約50%):中程度の苦味を感じる
• ノンテイスター(約25%):ほとんど苦味を感じない
つまり、同じ食材や飲み物でも、遺伝的に「まったく違う味覚の世界」が広がっているのです。
味覚の科学的な背景
研究によれば、味覚の差は大きく分けて以下の要因で生まれます。
1. 遺伝的要因
例:苦味受容体遺伝子(TAS2R38)の変異で苦味感度が数倍〜数十倍変化する。
2. 舌の解剖学的要因
舌の前方にある「茸状乳頭(fungiform papillae)」の数や密度が多い人は、味を強く感じやすい。
3. 年齢・性差
一般に、子供は大人より味覚に敏感。加齢とともに感度は低下するとされ、また、女性の方が味覚感度が高い傾向を示す研究も。
4. 生活習慣や環境
喫煙は苦味感度を鈍らせる。塩分・糖分を多く摂る習慣があると味覚の基準が変わる。
5. 心理・生理的状態
ストレスやホルモンバランスでも味覚は揺らぐ。
どのくらい差があるのか(定量的な例)
研究データを見ると、その差は想像以上に大きいことが分かります。
• 検出閾値(Detection Threshold)
同じ味物質で「120〜1,000倍」もの濃度差が報告されています。ある人には微量で味がするのに、別の人には100倍濃くしないとわからないのです。
• 差がわかる最小量(Just Noticeable Difference: JND)
食品例では、コーラの甘さを約9%減らすと消費者が差を検出できるという報告があります。つまり1割の調整で「味が変わった」と気づく人が出てくる。
• PROP/PTC実験(苦味感度)
スーパーテイスターはノンテイスターの10倍以上強く苦味を感じるという報告もあります。
Coffeeにおける味覚の個人差
この知見をCoffeeに重ねてみると、
• 浅煎りのコーヒーを「フルーティーで甘い」と感じる人がいる一方で、「酸っぱいだけ」と言う人がいる。
• 深煎りのCoffeeを「力強い」と楽しむ人と、「焦げ臭い」と嫌う人がいる。
こうした差は"嗜好の問題というより、感覚の受け取り方そのものが違う"と言えそうです。
プロのテイスター(Qグレーダーなど)は、訓練等によって味や香りをより細かく識別できるようになりますが、これは味覚そのものが大きく変わるのではなく、脳の解像度が上がる(解像度についての詳細は後述します)ことによるものだと考えられています。
ここまでのまとめ
• 味覚は遺伝・経験・環境によって大きく異なる。
• 苦味や甘味の感度は人によって数倍〜数十倍違う。
• 日常的なレベルでも約9%の味の変化で気づく人がいる。
• Coffeeの評価が人によって異なるのは必然であり、それこそが人の多様性を示している。
更に考えてみましょう。
Coffeeを飲み続ける事で変化すること
結論からいうと、Coffeeのように苦味・酸味・香りが複雑に絡む飲料を飲み続けることで、味覚の「感度」や「解像度」に変化が起こり得る、と考えられています。ただし、その変化にはいくつかの側面があり、研究的には「生理的な閾値の変化」と「経験による認知・学習の変化」に分けて整理できます。
1. 生理的な味覚感度の変化
• 閾値そのものが変わる可能性:
高塩分食で塩味の閾値が上がる(=濃くないと塩味を感じにくくなる)、高糖食で甘味の閾値が上がる、といった報告があります。同じようにCoffeeを頻繁に飲む人は、苦味や酸味の検出閾値が上がる(=鈍感になる)傾向が示唆されています。
→ 生理的「慣れ」による鈍化。
• 感覚順応(adaptation):
苦味や酸味を繰り返し摂取すると、瞬間的にも持続的にも「味が弱く感じられる」状態になることがあります。Coffeeを毎日飲む人が、他人よりも「苦味をそこまで強烈に感じない」のは、この影響が大きいと考えられます。
2. 認知的・学習的な変化(解像度の向上)
• フレーバー識別能力の向上:
ワインやCoffeeのテイスター訓練の研究では、繰り返しの学習によって「閾値はほとんど変わらない」が、「違いを区別し、言語化する能力」が向上することが確認されています。
→ これは「解像度の上昇」と呼べる側面。
例えば、以前は「ただ苦い」としか感じなかったのが、飲み続けるうちに「グレープフルーツのような苦味」「カカオ的な苦味」と差別化して表現できるようになります。
• 注意の向け方による違い:
味や香りの特定要素に意識を向けて訓練すると、その要素に敏感になります。これは脳の感覚処理のリソース配分が変化する結果と考えられています。
3. Coffee特有の要素
• Coffeeは苦味・酸味・甘味・うま味・渋味(ポリフェノール)・香気成分が同時に作用するため、飲み続けることで「混ざり合った味のどの部分に注目するか」を学習することができます。
• 特に「酸味」については、初心者は「酸っぱい=不快」と感じがちですが、飲み慣れると「明るい酸」「果実感」としてポジティブに評価できるようになる傾向が報告されています。
以上をまとめると
• 閾値(生理的な感度)は、繰り返し摂取で上がる(鈍くなる)ことがある。
• ただし「解像度(細かい違いを区別する能力)」は、経験や訓練によって大きく向上する。
• Coffeeを飲み続けると、「苦味や酸味の強さには鈍感になる」一方で、「風味や質の違いには敏感になる」二重の変化が起こり得る。
全く同じCoffeeを飲んでいても、そこに感じる世界は、人それぞれ。
上に記した通り、複雑な風味を持つCoffeeについての感じ方や捉え方はそれぞれに異なるので、定められた特定の評価基準の範囲を超えて、個々の味覚の差異を評価するようなことは本来できないはずです。
「良いCoffee」を誰よりも飲んでいるバリスタ、ロースター、テイスターでさえ好みのCoffeeはそれぞれに異なるのですから。
この事を前提とした上で、誰かと同じCoffeeを飲みながらその「感じ方の違い」について語り合ったり、自分だけにしか味わうことができない「最も美味しいCoffee」を探したりと、その違い自体を楽しむ事で、Coffeeを通し、更に新たな景色が広がっていく事でしょう。
Coffeeの届け手の一人としては、素晴らしい風味と品質と、味覚だけでは感じとる事のできない、多くの物語を含んだ特別なCoffeeをお届けできるように常に努めていますが、どんなCoffeeであれ、言うまでもなくその価値を、良し悪しを最終的に決めるのは貴方です。
何かに囚われる事なく、色々なCoffeeを様々な形で楽しむ。そこから、新たな景色が見えてくるかもしれません。
代表的な論文、参照、引用元
1. Nutrition Reviews(Temporal patterns…) — 個人差の大きさ(120〜1,000×)を示すレビュー的論考。
2. “Just noticeable difference in sweetness perception of cola” — 食品でのJNDの実測例(約9%)。
3. PMC: Association between Genetic Variation in the TAS2R38 … — TAS2R38とPROP感受性の関係(遺伝的説明)。
4. The Taste Detection Threshold (TDT) Test — 閾値測定法の手順・解説(方法論)。
5. “The Relationships Between Common Measurements of Taste Function” — 閾値・超閾評価・PROP・乳頭数など測定法の比較・関係。